糖尿病
糖尿病とは、血液中の血糖値(血中ブドウ糖濃度)が高くなり、その状態が長期間続く疾患です。正常な状態では、食事を摂ることで血糖値が上昇し、膵臓から分泌されるインスリンが働き、細胞内にブドウ糖が取り込まれることで、血糖値が下がります。しかし、糖尿病患者では、インスリンの分泌が不十分であるか、細胞の反応が弱くなっているため、血糖値が上がったままになります。糖尿病は、主に2つのタイプに分類されます。1型糖尿病は、若年で発症することが多く、自己免疫などにより膵臓からのインスリンの分泌が不十分になっているため起こる病気です。生活習慣は関係なく、不足するインスリンを毎日注射で補充する必要があります。
一方、2型糖尿病は、成人期に多く発生し、運動不足や食事などの生活習慣が原因となることが多く、治療には生活習慣の改善が大切な役割を担います。糖尿病になると、持続的な高血糖が身体に様々な影響を与えます。血管や神経、臓器などが障害を受け、心血管疾患、腎臓病、網膜症、神経障害など、様々な合併症を引き起こすことがあります。
糖尿病は自然治癒を期待できず、放置すると多くのリスクが発生するため、治療が大切です。高血糖は、細い血管だけでなく太い血管も障害し、動脈硬化を促進しますこのため、心筋梗塞や脳卒中などの心血管疾患のリスクが高くなります。また、腎臓病のリスク増加も挙げられます。
高血糖によって、腎臓の機能が低下する「糸球体硬化症」という病気が発生しやすくなり、進行すると腎臓の機能が失われる場合があります。
「なぜ目が?」と思われる方も多いのですが、高血糖によって、目の奥にある網膜の毛細血管が傷つき、網膜症という病気を引き起こすリスクが高くなります。
網膜症は、失明や視力低下の原因となることがあります。
他にも、神経障害のリスク増加が挙げられます。
高血糖は、末梢神経を傷つけ、神経障害を引き起こすリスクが高くなります。
神経障害は、手足のしびれや痛み、刺激感覚の低下、筋力低下などの症状を引き起こすことがあります。
このような放置リスクを踏まえると、糖尿病治療の重要性が分かって頂けるのではないでしょうか。
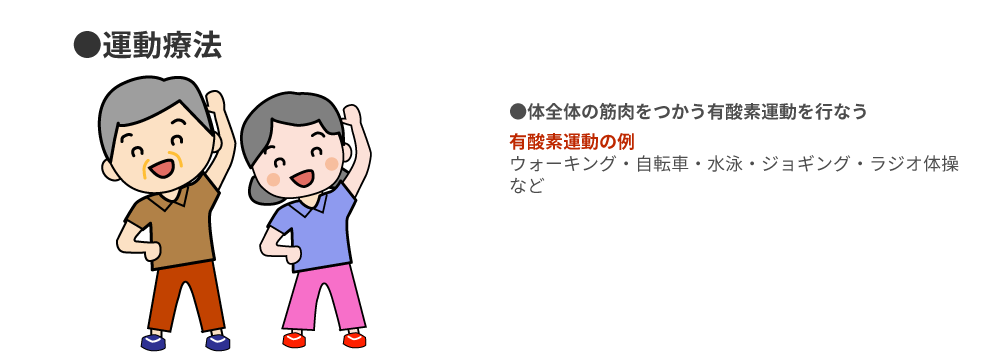
糖尿病の原因
インスリンが不足、あるいは分泌しなくなることで血糖値が高くなることが糖尿病の原因です。
ではなぜインスリンが不足するのかといえば、こちらもいくつかの原因が考えられます。
遺伝的な要因
糖尿病は、遺伝的な要因が関与すると考えられています。
親や兄弟姉妹に糖尿病がいる場合、自分自身が糖尿病にかかるリスクが高くなるとされており、特に2型糖尿病の場合はこちらが多いとされています。
肥満
過剰な体重があると、膵臓が必要以上のインスリンを分泌し、その結果としてインスリン抵抗性が高まってしまいます。
運動不足
運動は、筋肉の働きによって血糖値を下げる作用があります。
運動をすることで、筋肉の中のグルコースが消費され、血液中のグルコース濃度が低下します。
そのため、糖尿病患者は運動をすることで、血糖値をコントロールするよう指導されます。
また、運動はインスリンの効果を高める作用があります。
運動をすることで、筋肉の中のインスリン受容体の数が増え、インスリンの効果が高まります。
そのため、糖尿病患者は運動をすることで、より少ない量のインスリンで血糖値をコントロールすることができます。
食生活
食生活は糖尿病の最も大きな原因とされています。
過剰な脂質の摂取は、肥満を引き起こし、肥満は糖尿病のリスクを高めます。
糖質の過剰摂取は、血糖値を急激に上昇させ、膵臓がインスリンを分泌する量を増やすため、長期的には膵臓の負担を増やし、糖尿病を引き起こす可能性があります。
また、食事の質や種類も糖尿病の原因になることがあります。
例えば、加工食品や高脂肪・高糖質食品の過剰摂取、コーラやカルピスなどの甘い飲み物の過剰摂取、食事の時間帯の乱れなども糖尿病の原因となる可能性があります。
また、加齢に伴うすい臓機能の低下によって、インスリンの分泌量が低下し、糖尿病が発症するケースや、膵炎、膵癌などの疾患が糖尿病を招くケースもあります。
糖尿病の症状
糖尿病の症状は多岐にわたります。
まずは、多飲・多尿です。
血糖値が高いと、体内に余分な糖分がたまってしまい、喉の渇きを感じることから多飲、そして多飲に伴う多尿の症状があらわれます。
さらに高血糖の状態では膀胱炎、頻尿になりやすいです。
疲れやすさや倦怠感も糖尿病の症状の一つです。
糖尿病は、糖分が細胞に入りにくくなっているため、細胞がエネルギー不足に陥りやすくなります。
結果、疲れやすさや倦怠感を感じることがあります。
食欲不振を感じる患者もいます。
糖尿病になると、血糖値が高い状態が続くことから、食欲が低下することがあります。
免疫力の低下も見受けられます。
高血糖の状態では体の免疫に携わる白血球の働きが弱まります。その結果感染しやすい状態になります。膀胱炎や水虫などの感染症になりやすくなります。
さらには視力の低下があらわれる患者もいます。
糖尿病によって網膜がダメージを受けることで、視力の低下や視野の狭窄などの症状があらわれることがあります。
他にも皮膚のかゆみや乾燥があります。
糖尿病の治療方法
検査
糖尿病の検査方法には空腹時血糖値、食後血糖値、HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)などを測定することで、血糖値の異常を確認することができる血液検査、尿中の糖やケトン体を測定することで、糖尿病の疑いがあるかどうかを確認することができる尿検査、皮膚に挿入したセンサーから24時間、血糖値の変化を測定することで、血糖値の変動を把握することができる経皮的連続グルコースモニタリング(CGM)、空腹時血糖値を測定した後、グルコースの液体を飲ませ、その後1時間、2時間後の血糖値を測定することで、糖尿病の疑いがあるかどうかを確認することができるオーラルグルコース負荷試験(OGTT)が挙げられます。
検査の結果、空腹時血糖値が126mg/dL以上、HbA1cが6.5%以上、OGTTで、食後2時間以内の血糖値が140mg/dL以上でグルコース耐性がある場合、糖尿病だと診断します。
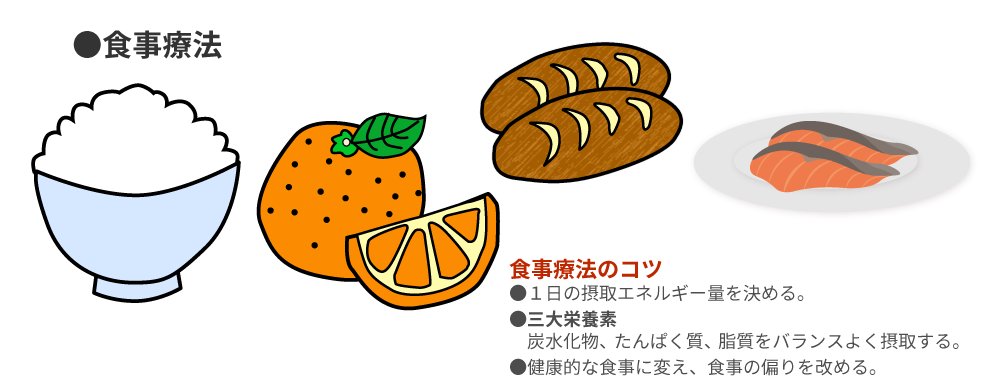
治療
糖尿病の治療法として、まずは生活習慣の改善が重要です。
定期的な運動やバランスの良い食事が基本です。
生活習慣の改善で効果がない場合、糖尿病薬の内服を始めます。
インスリンを分泌する薬、SGLT-2阻害薬という血中の等を尿に排出する薬、インスリンの効きをよくする薬などの薬を用います。
また、比較的新しい薬で、インスリンの分泌を増加させつつ、食欲減退効果があり、減量(ダイエット)の効果があるGLP-1作動薬も治療に使うことがあります。
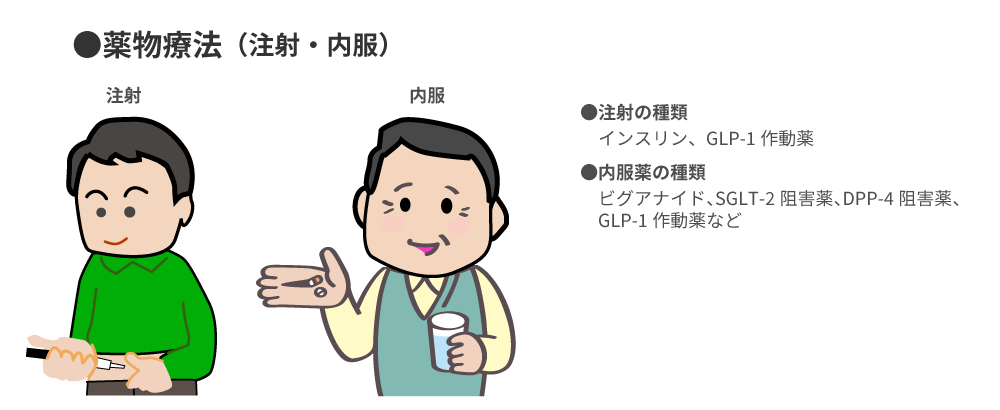
内服薬で調整できない場合、インスリン注射を追加します。
インスリンは、血糖値を下げるホルモンであり、糖尿病の治療には欠かせないものです。
これらすべてに共通しているのは、継続性です。
糖尿病は一朝一夕に改善される疾患ではなく、継続することが大切です。
その点では担当の医師との信頼関係も重要です。
分からない点や不安がある場合には、かかりつけの医師に相談して状況に応じた適切なアドバイスをもらいましょう。
基本情報
住所:〒116-0001
東京都荒川区町屋4-8-4
最寄駅 都電荒川線 東尾久三丁目駅から徒歩3分
電話番号 03-3895-5365
※土曜日の診療時間は12時まで行っております。
休診日:土曜午後・日曜・祝日

住所
東京都荒川区町屋4-8-4
電話
診療項目
内科・消化器内科・皮膚科・泌尿器科・各種検診
診療時間
平日 9:00 ~ 12:30 16:00 ~ 19:00
土日祝日 9:00 ~ 12:00
休診日
土曜午後・日曜・祝日